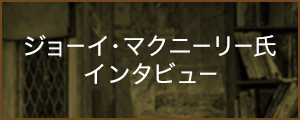『ウェストサイド物語』誕生秘話
“永遠の青春神話”『ウエストサイド物語』。戦後ミュージカルシーンに
決定的な変化をもたらしたこの劇薬は、いかにして生まれたのでしょうか?
ブロードウェイを震撼させ、日本列島に衝撃を走らせ、今なお新鮮な驚きと
感動に満ちた傑作ミュージカル。その現在に至るまでの歴史を、数回に分けて
たっぷりとご紹介します。
- 3人の神話の生みの親
- 構想8年7カ月ー全米を震撼させた衝撃の開幕
-

『ウェストサイド物語』制作当時のクリエイティブスタッフたち (左から)スティーヴン・ソンドハイム(作詞)、アーサー・ロレンツ(台本)、2人挟んで、レナード・バーンスタイン(作曲)、ジェローム・ロビンス(演出・振付)
『ウエストサイド物語』の初演は1957年。
しかし、その構想が持ち上がったのは遡ること8年前、第二次大戦後まもなくの1949年のことでした。この神話の生みの親となったのは、ジェローム・ロビンス(演出・振付)、レナード・バーンスタイン(作曲)、アーサー・ロレンツ(台本)の3人。ほぼ同級生の彼らは、当時30歳を迎えたばかりの若者に過ぎませんでした。
しかし、若い彼らだからこそ、戦後という時代の空気を痛いほど敏感に感じ取っていたのでしょう。さらに特筆すべきは、彼らはその若さにして、すでに一流の仕事を成し遂げた真のプロフェッショナルだったことです。
ジェローム・ロビンスは、クラシックバレエの名門「アメリカン・バレエ・シアター」の前身である「オリジナル・バレエ・シアター」でダンサーとして活躍した後、新進気鋭の振付家としてブロードウェイの寵児となっていました。
一方、レナード・バーンスタインは、こちらもクラシック音楽の名門ニューヨーク・フィル・ハーモニーの指揮を弱冠25歳の若さで任されるほどの天才音楽家。しかし、クラシックの世界に飽き足らず、彼もまたブロードウェイに新天地を求めていました。
そして、この2人の天才が『ロミオとジュリエット』を下敷きとして、まったく新しいミュージカルを作り上げたいと志した時、信頼を置いたのが同世代の劇作家アーサー・ロレンツだったというわけです。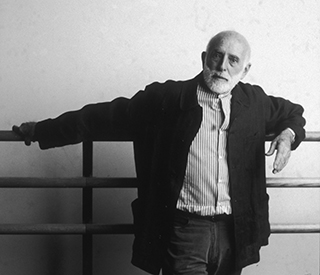
ジェローム・ロビンス
さらに、この3人がブロードウェイで『ウエストサイド物語』を作り上げたことには、若い世代の台頭という以上に大きな意味があります。
それは、彼らがアメリカ生まれのアメリカ育ちという点です。繁栄と恐慌、さらに激しい戦争というアメリカのリアルを肌身に感じながら育った3人。
その彼らが作り上げた舞台だからこそ、ブロードウェイの老練な観客の度肝を抜き、市井に暮らす人々の大いなる共感を呼び起こし、ミュージカル界に新たな夜明けを告げる革命を起こすことができたのです。
レナード・バーンスタイン
こうして、3人はその奇蹟の邂逅によって『ウエストサイド物語』という神話を生み出した後、彼らの才能を求める世界へと別々の道を歩んでいくことになります。
ジェローム・ロビンスは、『ジプシー』『屋根の上のヴァイオリン弾き』などの名作を送り出してから、再びバレエ界へ。
レナード・バーンスタインは、20世紀後半を代表するクラシック音楽家として歴史に名を刻みました。
そして、アーサー・ロレンツは『追憶』『愛と喝采の日々』などの傑作により映画界の重鎮に。2011年、3人の中で最後まで存命していたアーサー・ロレンツが亡くなり、本当に"神話"となった『ウエストサイド物語』。
戦後のミュージカル界のみならず、文化・芸術の担い手となった天才たちの若き日の情熱の滾りを、現代に生きる私たちがしっかりと受け継いでいく時が来ているのかも知れません。 -

1957年ブロードウェイ初舞台
「熱狂的支持は急速に広がり、至るところでミュージカル・ファンを刺激した。この作品が第一級の成功作だという評価を得るにはそう時間はかからなかった」
ニューヨーク・タイムズで健筆を振るい、ブロードウェイにその名を冠した劇場が建てられたほどの舞台批評家ブルックス・アトキンスンは、『ウェストサイド物語』初演時のセンセーションを、後日こう回想しています。その後のミュージカルシーンを一変させることになった、運命の初演は1957年9月26日。
一体『ウェストサイド物語』の中に秘められた何が、当時の観客たちを震撼、熱狂させ、そして神話とまで称されるようになったのでしょうか?1957年ブロードウェイ初舞台
まず、何といっても物語に込められたメッセージ性の高さと衝撃度。
『ウェストサイド物語』以前のミュージカルは、愛と平和で満ちた理想の世界を描いたハッピーエンドのラブコメディが主流であったのに対して、この作品の舞台は荒みきったスラム街。しかも、そこに描かれていたのは、当時のアメリカのタブーである人種間の差別や対立といった社会問題でした。
台詞や歌詞にも「Wop(イタ公)」や「Spik(スペ公)」といった俗語や卑猥な表現が散りばめられ、そのリアリティと生々しい迫力は、まさにギャングの若者たちが振るうナイフの切っ先のように観客の心に深く突き刺さったのです。しかし、若き表現者たちにとって、権威あるブロードウェイのタブーに挑戦するにはそれなりの覚悟も必要でした。作曲家レナード・バーンスタインは、創作日誌にこう記しています。
「全貌が露わになるまで、十分に香料につけ燻製にして吊るし、森の中で寝かせておいたほうがいい。問題の多い仕事は時間をかければかけるほどうまくいくものだ」"シェイクスピアの傑作『ロミオとジュリエット』の現代版をミュージカルで"という構想が持ち上がってから、開幕に到達するまでに費やした歳月は実に8年7カ月!
それほどまでに熟成させることができたのは、いかに彼らがこの舞台に芸術家としての覚悟と矜持を賭けていたかという証左でもあります。
(上)稽古の様子 ピアノを弾くソンドハイム、指揮はバーンスタイン。
(下)俳優達とロビンス(左から2番目)さらにタブーへの挑戦は、物語だけに留まりません。
それまでのミュージカルはシンガーとダンサーの分業制で、ダンスはあくまで歌の添え物でしかありませんでした。しかし、『ウェストサイド物語』では、主人公たる若者たちがその肉体を躍動させ、その想いの丈を自分自身で歌い上げます。
この、今では当たり前となっている"ひとりの俳優が歌とダンスの両方をこなす"という表現方法は、『ウェストサイド物語』によって確立されたものなのです。
しかも、この舞台に出演する俳優たちに求められたのは、ダンス・音楽ともに極めて洗練されたハイレベルなもの。それもそのはず、ジェローム・ロビンスとレナード・バーンスタインの2人は揃ってクラシックの世界で一流のプロであり、そこに妥協はありませんでした。「私は信じられない、四十人の若者たちがステージの上で現にこうして演じてくれているなんて!一度も歌ったことのない若者たちが、五声の対位法を歌っているのだ――天上の響きをもって」
「トゥナイト」「アメリカ」「サムウェア」などミュージカル史に残る難曲かつ名曲に溢れた音楽ですが、当時のバーンスタインの創作日誌には、不可能が可能となったことへ彼自身が驚き、感動に震える姿が記されています。また、高度なテクニックに加えて豊かな物語性を与えられたダンスは、それまでの"添え物"から"表現の核"へと一変することになります。
プロローグでは、ジェット団の縄張りだったウェストサイドにシャーク団が移り住み、抗争が始まるまでの過程がダンスによって表現されます。
そして、イタリア系のジェット団は優雅なダンスで、プエルトリコ系のシャーク団は力強いダンスで火花を散らし、若者たちは鋭く乾いたフィンガースナップを響かせることで、行き場のないフラストレーションを舞台に叩きつけるのです。俳優たちが、今この瞬間を生きる若者として舞台で歌い踊り、青春を駆け抜ける。
だからこそ、刺激的なメッセージがストレートに真実味をもって観客に伝わり、ミュージカルの新しい夜明けを告げることになった『ウェストサイド物語』。
この燃えるような情熱と身を切り裂くような切なさに満ちた神話は、そのあまりの革新性ゆえにトニー賞は2部門(振付・美術)のみの受賞となりましたが、初演は伝説の舞台として語り継がれ、1961年の映画版の大ヒットにより名実ともに世界的傑作となったのです。
Copyright SHIKI THEATRE COMPANY. 当サイトの内容一切の無断転載、使用を禁じます。